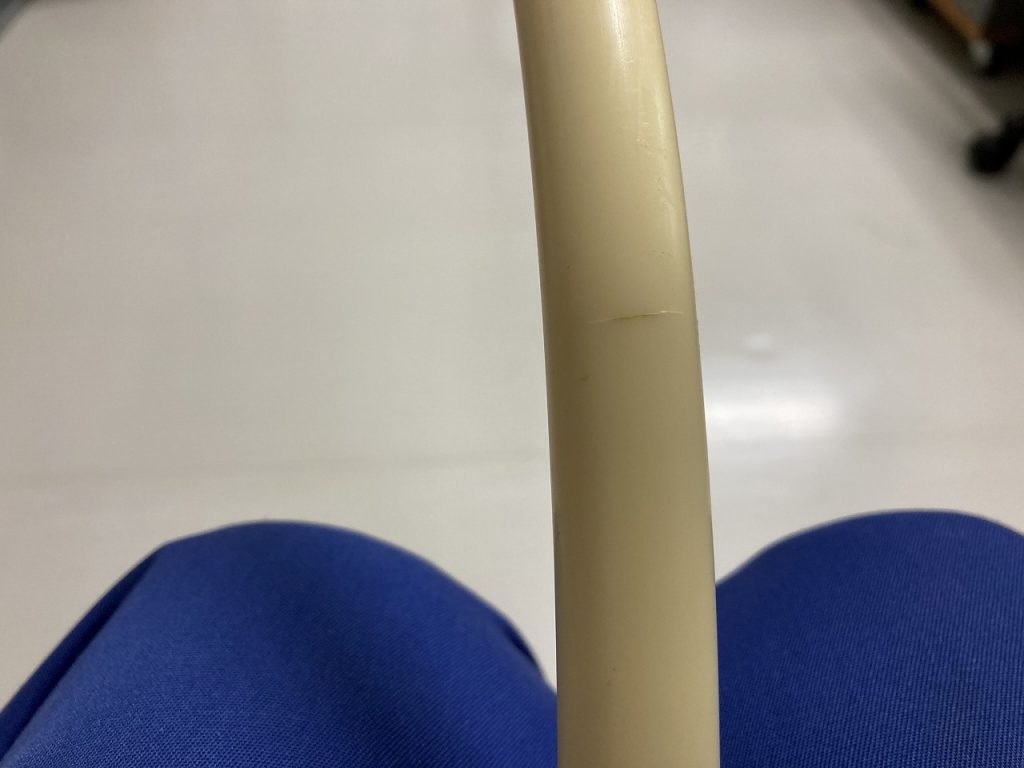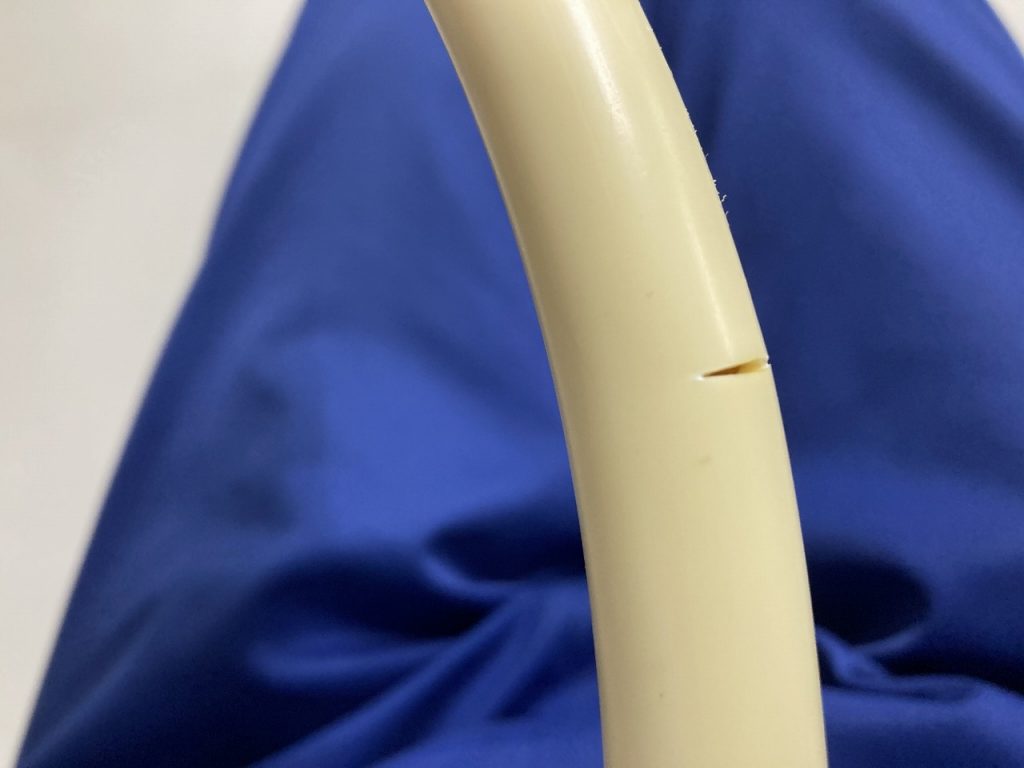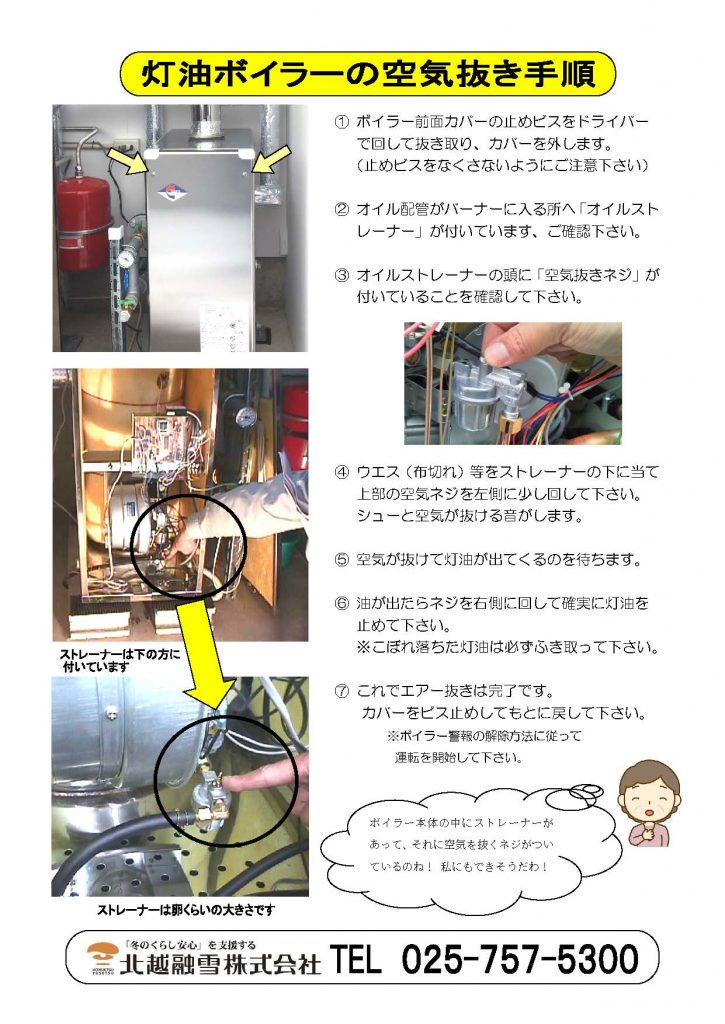新潟県十日町市のN様より
「仕事が忙しいので屋根融雪にしたい」
とご相談を頂きました。
十日町市は長野県にほど近い人口約5万人の町で
2月の最深積雪量は210?です。(1991-2020)
上空から見回しても、雪、雪、雪…。
本当にあたり一面が銀世界です。
社会科の教科書にも「日本屈指の豪雪地」
として掲載されるほどのこの地では
多い時には1日で数十?もの雪が
降ることも珍しくありません。
電気ヒーター式融雪でそれに対応しようとすると
1m2あたり300?350Wもの大きなエネルギーが
必要になるため、30坪(約100m2) クラスの住宅でも
30kW級の設備となり、大雪の年も、小雪の年も
設備容量に応じた基本料金が負担となります。
その点、ボイラー等を熱源とする温水循環式では
温度調整で出力を自在に変更でき、
小雪の年には燃料代がグッとお安くなるため
豪雪地には温水式が向いています。
今回は屋根のリフォームも併せて行うため
融雪パネルを板金の下に隠蔽しました。
屋根面が均一に暖まることで
ムラなくきれいに雪が消えています。
N様ご自身は建設会社の社長で、
冬季間は地域を守る道路除雪を担っておられるため、
ご自宅の雪は どうしても一番後回しになってきたとのこと。
そんな経緯から、今回思い切って屋根融雪にすることを決心されたそうです。
新築住宅はもちろん、既存住宅でも
雪のお困りごとは私たちがご相談に乗ります。
フリーダイヤル 0120-028-119 まで
どうぞお気軽にご相談ください。