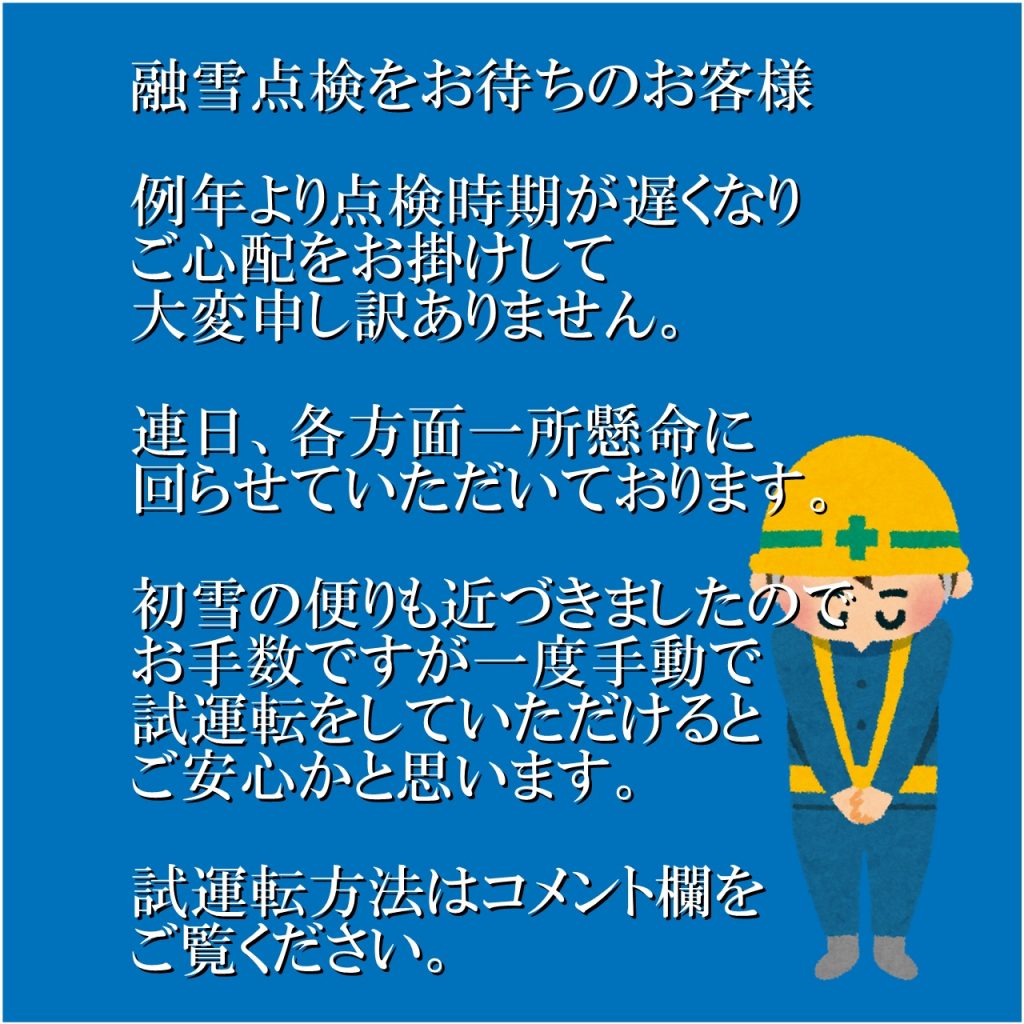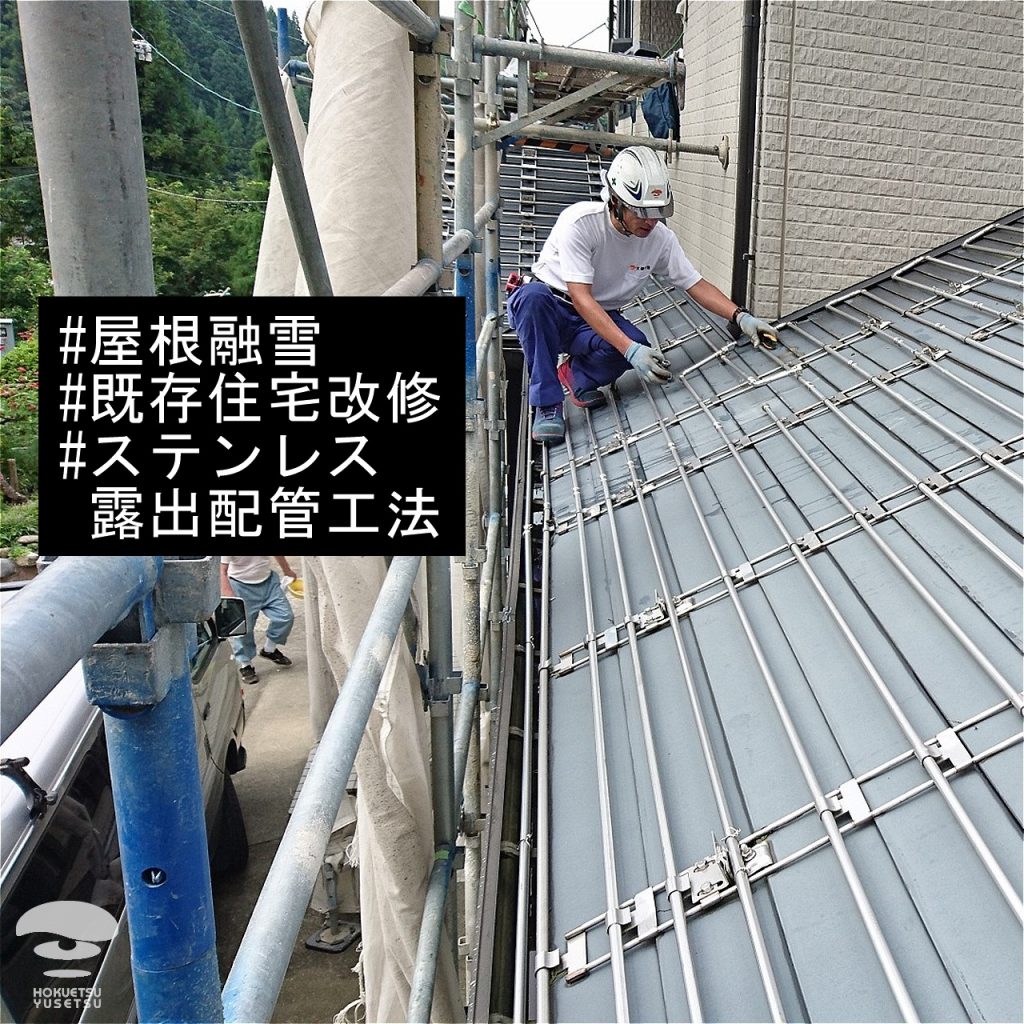今年もまた雪のシーズンになりました。
初雪が降る前に、試運転を済ませておきましょう。
まず、機械周りの事前チェックです。
事前チェック? 煙突に可燃物が触れていないこと。
事前チェック? 圧力計が0.06MPa以上を指していること。
1.燃料
灯油の場合:タンクに燃料を補給してください。
燃料補給が済んだら、?タンクのそば、?ボイラーのそばのコックを開けます。
ガスの場合:?ガスメーターの元栓、?ボイラーのそばの栓を開けます。
2.電源
コンセントプラグを差し込みます。
?制御盤(リレー盤)用、?ボイラー用と最低2本あります。
一見差さっているように見えても、実は抜けかかっていることもあるので確認しましょう。
3.制御盤
前蓋を開けると左側に小さなブレーカーがあります。
ブレーカーを上げると、緑色の小さなLEDが灯ります。
4.ボイラーリモコン
ボイラーリモコンをONにします。
リモコンはボイラー前蓋かボイラーすぐそばの壁にあります。
電源を入れると緑色のランプが灯ります。
リモコンに「注意:ボイラーリモコンは警報解除以外操作しないでください」とシールが貼ってある場合は、消灯のままで結構です。
5.融雪コントローラー
融雪コントローラーをONにします。
コントローラーは機械室または玄関・リビングの壁などにあります。
電源を入れると緑色のランプが灯ります。
6.試運転
融雪コントローラーで【手動運転】を行います。
まずポンプが動き、続いてボイラーが着火します。
設定温度まで暖まるとボイラーは一旦止まります。
屋根融雪では 高温側:60℃、低温側:45℃
路面融雪では 高温側:35℃、低温側:20℃
を目安に運転してみてください。
外気温にもよりますが所要時間は30分?1時間程度です。
トラブル事例? ボイラーに着火しない
ボイラーリモコンがONになっているか(手順4)ご確認ください。
灯油切れによる灯油配管の空気溜まりでも不着火が起こります。
トラブル事例? ボイラーがすぐ止まる
循環液不足か、融雪管への空気溜まりの可能性があります。
トラブル? ポンプが動かない
制御盤の運転切り替えスイッチがOFFの可能性があります。
スイッチONでも動かない場合はポンプ内の羽根車が固着している可能性もあります。
トラブル? 【 自動運転 】が出来ない
自動運転はセンサーが雪を検知して動きます。
実際の降雪をお待ち下さい。
ご判断がつかない場合は北越融雪フリーダイヤルへお電話ください。
フリーダイヤル☎0120-028-119です。